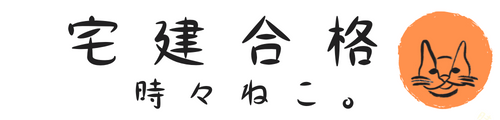「意思表示」は難しくない!初心者はとりあえずこれ先に覚えて。[宅建試験2023]

「意思表示」の分野は過去10年間で5回出題されています。
ここの分野では民法用語特有の専門用語がたくさんでてきます !
つまり言葉の意味をまず理解しないと、

そもそも問題の意味が分からへん・・
ということになります。そんなことにならないよーに、
この記事では、
・暗記すべき箇所は表にまとめ、
・暗記でまかなえない箇所はその根拠を述べインプットしやすく、
解説していきまーす。
はたまた、
覚えるべき箇所は表にまとめたよ!
無料でPDFもダウンロードできちゃうよ!

漢字も読めないお馬鹿さんだったけど、独学2回目でなんとか宅建合格し、不動産屋さん歴11年目の寝子です。完全初心者~ほぼ初心者でも理解できるように分かりやすく解説していきます!
なるべくお金を掛けずにできる勉強方法とかも書いていく予定でーす
目次
01 とりあえずこれ先理解して:基本の言葉

今回出てくる民法特有の言葉たちです。とりあえずは言葉の意味を理解できたらおけです!(ゆくゆくは必ず覚えてねん)
| 民法用語 | 意味 |
| 善意(ぜんい) | 知らない |
| 悪意(あくい) | 知っている |
| 過失(かしつ) | 落度、うっかり |
| 善意無過失(ぜんいむかしつ) | 知らないし、知らないことに過失もない |
| 善意有過失(ぜんいゆうかしつ) | 知らないが、知らないことに過失がある |
| 対抗(たいこう) | 主張 |
| 有効(ゆうこう) | (契約が)ある |
| 無効(むこう) | (契約が)ない |
02「意思表示」
①詐欺(さぎ)~騙されて契約してしまったら

原則:詐欺にあって(騙されて)契約を結んだ場合、被害者はその契約を取り消すことができます。
※例:BがAを騙しAの土地を買い取る契約をした場合。
→Aはこの契約を取り消すことができます!すでに土地を引き渡していたとしても、土地を取り戻すことができます。
●例外● 善意無過失の第三者には対抗できません。
先ほどのABの例で説明しますと、
※例:AがBとの契約を取り消す前に、Bがこの土地をCに売って(転売して)いた場合
(C=第三者)
・パターン⓵ Cが悪意(AがBに騙されたことを知っていた)OR善意有過失(知らなかったことに落度がある)の場合
→AはCから土地を取り返せます!
・パターン② Cが善意無過失(AがBに騙されたことを知らず落度もない)の場合
→AはCから土地を取り返せません!

騙されたAにも多少の落度はあるから、Cが何も知らなくて、落度もない場合はCを守る方が優先されるんだね。
この回自体はそんなに難しくはないですが民法特有の言葉が当たり前のように使われるので、冒頭で説明した言葉の意味は理解して、慣れておきましょっ☆
②強迫(きょうはく)~脅されて契約してしまったら

原則:強迫されて契約させられた場合、被害者は契約を取り消すことができます。
※例:BがAを強迫し、Aの土地を買い取る契約をした場合。
→Aはこの契約を取り消すことができます!すでに土地を引き渡していたとしても、土地を取り戻すことができます。
さっきの詐欺と違うのは、
善意無過失の第三者にも対抗できるということ!
(第三者はAがBに騙されたことを知らないし、知らないことに落度もない)
第三者が気の毒な気がしなくもないですが、強迫の場合Aはおどされた被害者ですので、徹底して守ることになってます!

この詐欺と強迫の違いは割と試験に出てるYO!!
③錯誤(さくご)~勘違いして契約してしまったら※2020.民法改正
錯誤とは勘違いのことです!

原則:錯誤による契約は重大な勘違いだった場合取り消すことができます。
※例Ⅰ:Aが甲土地と乙土地2つの土地を持っており、Bは甲土地の方を買いたいと思っていたのに、勘違いで乙土地を買うと言ってしまった場合。
→重大な勘違いなのでBは契約を取り消すことができます!
この重大な勘違いがあることを「錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである」と言ったりします・・が、長すぎるので頭の片隅に置いといてください。
●例外●↑の例のような重大な錯誤であっても表意者(勘違いした人のこと。ここではB)に重過失があった場合は自業自得なので取り消せません。

注意!!通常の過失ではなく重過失です!
●例外の例外●
が、表意者に重過失があった場合でも以下の時は取り消しができます。
表意者が重過失でも取り消せるパターン
1⃣相手方が悪意OR重過失。
2⃣相手方が表意者と同じ勘違いをしていた。(共通錯誤)
表意者に重過失があったとて、悪意・重過失の相手方まで保護する必要はないからですね。
|錯誤の種類:動機の錯誤(どうきのさくご)
錯誤の種類でもうひとつ✍
動機の錯誤(どうきのさくご)というものがありまして!
そのままですが、動機に錯誤がある場合のことを言います。
※例:Aが所有する甲土地の近くに新駅ができる(←これが動機!)という噂を信じたBがAから甲土地を買った。だがしかし、その新駅はできなかった場合。
・パターン⓵Bが動機を表示していた(「甲土地の近くに新駅ができるので甲土地を売って下さい」とAに言うた)場合
→取り消せる。
・パターン②Bが動機を表示していない(「甲土地を売って下さい」とだけAに言うた)場合
→取り消せない。
そして、錯誤の取消しは、善意無過失の第三者には対抗できません。

そろそろごっちゃになる予感がする第三者との関係あれこれは下の方のページにあるPDFに表でまとめてあるよ!
|例題を解いてみましょー。(錯誤 R2.10月.問6)
Q:Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合AはBに対し、錯誤による取消しができるか。
→取り消しできます!
「贋作であるので、10万円で売却する」とAはBに動機の錯誤を表示しているからです。
Aの過失の有無が書いていませんが、「Bも同様に贋作だと思い込み」とあるので2⃣の共通錯誤にあたるのでどちらにせよ、取り消しできます!
④虚偽表示~嘘の契約をしたら
虚偽表示とは「相手方と示し合わせて(通謀)嘘の契約をすること」です。
虚偽表示による契約は無効になります。
※例:借金まみれのA Aは自分が所有している土地を借金取りに取り上げられないようにするためBと通謀し、その土地をBに売ったことにした。
→虚偽表示(AB間の契約は嘘の契約であり、お互いに土地をやりとりする意思はない)なのでその契約は無効です。
たとえ登記名義をBに移転していても無効です。
●原則●そして、お決まり虚偽表示の無効は、善意無過失の第三者には対抗できません。
※例その後①: BがこのAの土地を第三者Cに転売した場合 。
→たとえCが所有権移転登記*1を得ていなくても、Cに過失があったとしても、AはCに虚偽表示の無効を対抗できません。
できるのは、Cが悪意(虚偽表示の事実を知っていた)の時だけです!

Aを保護する必要はないからね。
そして、ややこしいことに
さらに4人目Dが現れた場合のお話です!
※例その後②:Aの土地は、AとBの虚偽表示によってBに譲渡されました。
が、その後Bが土地を第三者Cに転売しました。
で、その後また Cが D に転売してしまいました。さて Aは Dに虚偽表示だから無効だ、と主張できるのでしょうか?
→答え:CもしくはDどちらか一人でも善意なら対抗できません。
| C | D | AVS D (どちらが勝つか) |
| 善意 | 善意 | D |
| 善意 | 悪意 | D |
| 悪意 | 善意 | D |
| 悪意 | 悪意 | A |
つまり👆こゆことです。
考えすぎの貴方は、「なんでDが悪意のときもDは保護されるんよ!??」ってなるかもしれませんが、
Dを保護しないと善意のCが損害を受けることになるので、Cを保護する意味でDを保護しています。

Aが勝てるのは、両方(C&D)が悪意のときだけ!!
|例題を解いてみましょー。(虚偽表示 H7.問4 )
Q:AとBが、A所有の土地について、所有権を移転する意思がないのに通謀して売買契約を締結し、Bの名義に移転登記をした。Bがこの土地をDに売却し、所有権移転登記をした場合で、DがAB間の契約の事情を知らなかったことについて過失があるときは、Aは、Dに対してこの土地の所有権を主張することができるか。
→できません!虚偽表示において第三者の対抗を判断するのは善意か悪意かだけです。過失の有無は関係ありませんよっ。
騙されないで~
⑤心裡留保(しんりりゅうほ)~冗談で契約したら
冗談のつもりで言ったことを心裡留保と言います。
心裡留保による契約は相手が善意無過失の場合は有効になります。
※例:Aが自己所有している時価1億円の土地を冗談のつもりで(👈心裡留保)「5,000万円で売る」とBに言った場合。
・ Bが善意無過失の場合→契約は有効
・ B が悪意または有過失の場合→契約は無効
そして毎度お決まりの善意の第三者ですが、
心裡留保の無効は、善意無過失の第三者には対抗できません。(契約の無効を主張できません)
|例題を解いてみましょー。(心裡留保 H19.問1 )
Q:Aは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなく、Bもその旨を知っていた。この場合、Bが「1,000万円で購入する」という意思表示をすれば、AB間の売買契約は有効に成立するか。
→しません!!「Bもその旨を知っていた」(=悪意)とあるので契約は無効です。
03 まとめとPDF

| 民法用語 | 意味 |
| 善意(ぜんい) | 知らない |
| 悪意(あくい) | 知っている |
| 過失(かしつ) | 落度、うっかり |
| 善意無過失(ぜんいむかしつ) | 知らないし、知らないことに過失もない |
| 善意有過失(ぜんいゆうかしつ) | 知らないが、知らないことに過失がある |
| 対抗(たいこう) | 主張 |
| 有効(ゆうこう) | (契約が)ある |
| 無効(むこう) | (契約が)ない |
| 意味 | 第三者に対抗できるか | |
| 詐欺(さぎ) | 騙すこと | 第三者が善意無過失なら✖ |
| 強迫(きょうはく) | 脅すこと | 〇 |
| 錯誤(さくご) | 勘違いすること | 第三者が善意無過失なら✖ |
| 虚偽表示(きょぎひょうじ) | 嘘の契約をでっちあげること | 第三者(4人目も)が善意なら✖ |
| 心裡留保(しんりりゅうほ) | 冗談のつもりで言ったこと | 第三者が善意なら✖ |
★ここからダウンロードできます★意思表示と第三者の関係まとめ

民法特有の言葉(善意とか悪意とか)は丸覚えをする、というよりは使いかたに慣れていこうねっ
はじめは聞き慣れないので難しく感じますが、問題を解いていくうちに段々慣れていくので大丈夫っ
過去問でおさらいもしてね~