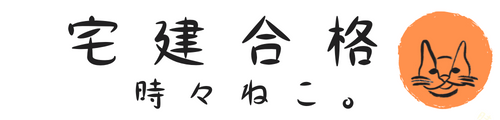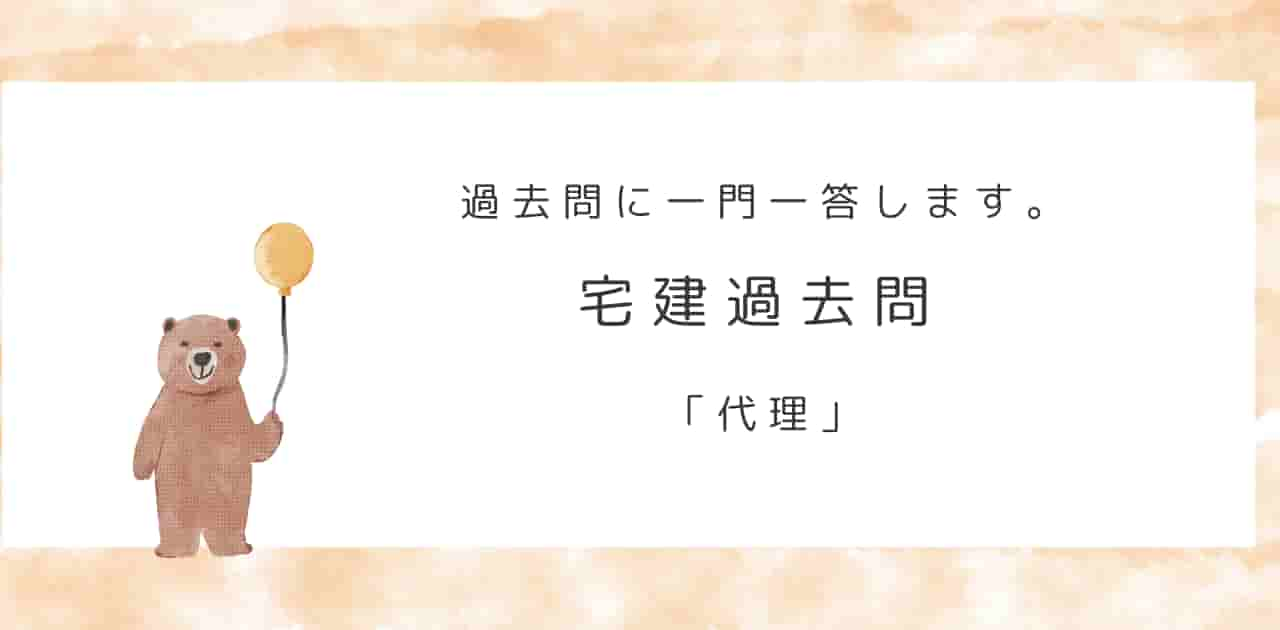初心者でもわかる「無権代理」分かりやすく解説します![宅建試験2023]
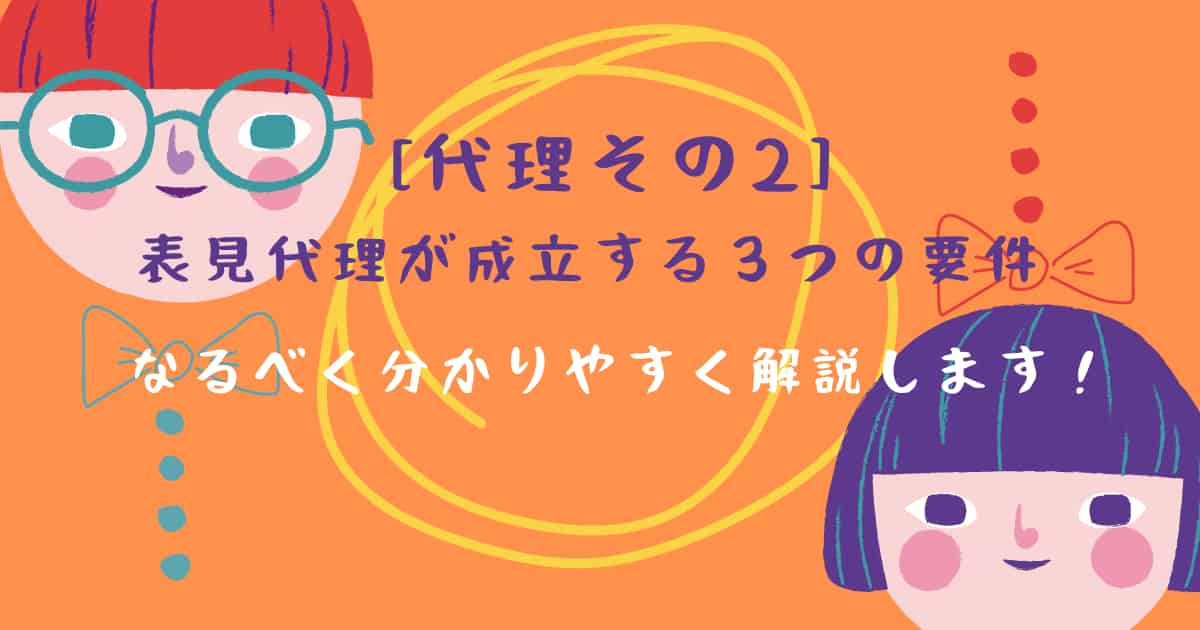
無権代理も出題回数が多い箇所です!
前回の代理が基礎になるので、しっかり頭で理解してから今回の無権代理に挑みましょ~!

漢字も読めないお馬鹿さんだったけど、独学2回目でなんとか宅建合格し、不動産屋さん歴11年目の寝子です。完全初心者~ほぼ初心者でも理解できるように分かりやすく解説していきます!
なるべくお金を掛けずにできる勉強方法とかも書いていく予定でーす
目次
1| 無権代理とは

無権代理とは代理人ではない人が代理人のふりをして行った契約のことです。


↑この立場のAのことを本人、Cのことを相手方という呼び方をします。
無権代理は原則として無効になります。つまり、この図でいうとAは家をCに引き渡す必要はありません!
●無権代理が有効になるパターン
しかし無権代理人の結んだ契約が本人にとって有利な場合もあり得ます。
その場合本人は無権代理行為であっても事後に承認することができます。そのことを追認(ついにん)と言います!
追認は、無権代理行為の時点にさかのぼって有効になります。
●無権代理の相手方保護
無権代理人と契約をしてしまった相手方はどうなるのでしょうか。
🔑無権代理の相手方を保護する3つの制度
1⃣催告権(さいこくけん)
相手方は本人に対して、相当の期限をつけて追認するか否かを催告することができます。(相手方が無権代理について悪意でも催告をすることができる)
※本人Aが期限までに答えない場合→追認を拒絶したものとみなされます。
2⃣取消権(とりけしけん)
相手方は、本人が追認しない間は、無権代理による契約を取り消すことができます。(相手方が無権代理について善意の場合だけできる)
3⃣履行請求権(りこうせいきゅうけん)・損害賠償請求権(そんがいばいしょうせいきゅうけん)
相手側は、本人の追認がない間は無権代理人に契約の履行OR損害賠償を請求できます。(相手方が無権代理について善意無過失の場合にできる)
※無権代理人が悪意なら相手方が善意有過失でも履行OR損害賠償を請求できます!!
ここでややこしいのは、善意・悪意・有過失の有無によって使える権限が違う、ということ。

その前に善意・悪意ってなんやっけ・・て人は「意思表示」でおさらいしてね👇
2| 表見代理とは
表見代理(ひょうけんだいり)とは、無権代理の一種で、実際には代理権がないのに、はたから見ると代理権があるかのように見えるケースです。
表見代理が成立すると、無権代理だったものを有効な代理行為として扱うことができます。
●表見代理が成立するには
本人の落度と相手方の善意無過失、この二つの条件が揃うと表見代理が成立します。
🔑本人の落度になる3つのパターン
1⃣代理権授与表示(だいりけんじゅよひょうじ):実際には無権代理人に代理権を与えていないのに、本人が「代理権を与えた」と表示した場合。(例 白紙の委任状を渡す等)
2⃣権限外の代理行為:無権代理人が代理権限外の契約をした場合。(例 本人は賃貸の代理権を与えたのに、無権代理人は相手方に売却をしてしまった)
3⃣代理権消滅後の代理行為:Bの代理権が消滅した後に、その代理権の範囲内で代理行為をした場合。
この3ついずれかのパターン+相手方が善意無過失の場合、表見代理が成立します👀
例題:表見代理
・問題(令和2年12月 問2):AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。→誤り
本人Aの落度と相手方Eの善意無過失、この二つの条件が揃うと表見代理が成立します。
Bの代理権が消滅した後にその代理権の範囲内で代理行為をする行為(甲土地をEに売却)は3⃣代理権消滅後の代理行為になるので、Eが善意無過失であれば、AはEに甲土地を引き渡す責任を負うことがあります。
3| 代理権の消滅
●代理権がなくなるとき
代理権が消滅するのは以下の5パターンのときです。
・本人→死亡・破産(任意代理のみ)
・代理人→死亡・破産・後見開始の審判
*本人が破産しても法定代理の場合の代理権は消滅しません。
任意代理・法定代理のおさらいはこちら↓
例題:個人的にごっちゃになった問題

・問題(H30年問2)
①AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。
→誤り
②AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。
→正しい
①の場合、Bは代理権を授与される前に補助開始の審判を受けています。
つまり、Aは被補助人であるBに代理権を与えたということになります。制限行為能力者も代理人になることができるので誤りです。
民法第102条
[代理人の行為能力]
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
② 代理人Bが後見開始の審判を受けた場合、代理権は消滅します。
その時点で代理権は消滅するので、記述の通りBがその後した行為は無権代理行為となります
民法第111条
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
1本人の死亡
2代理人の死亡又は代理人が破産手続き開始決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

②のBは、代理権を授与された後に後見開始の審判を受けているから、①のケースとは異なるよ。
| まとめ
これにて代理は終わりになります☆
難しそうに思えますが、登場人物それぞれの立場に立って客観的に考えた時に、割と想像できる範囲内の内容じゃないかなーと個人的には思います!
出題回数も多い箇所なので必ず過去問もCHECKしましょ~