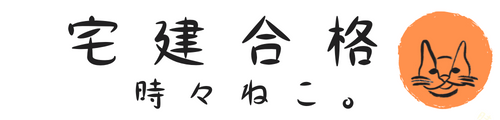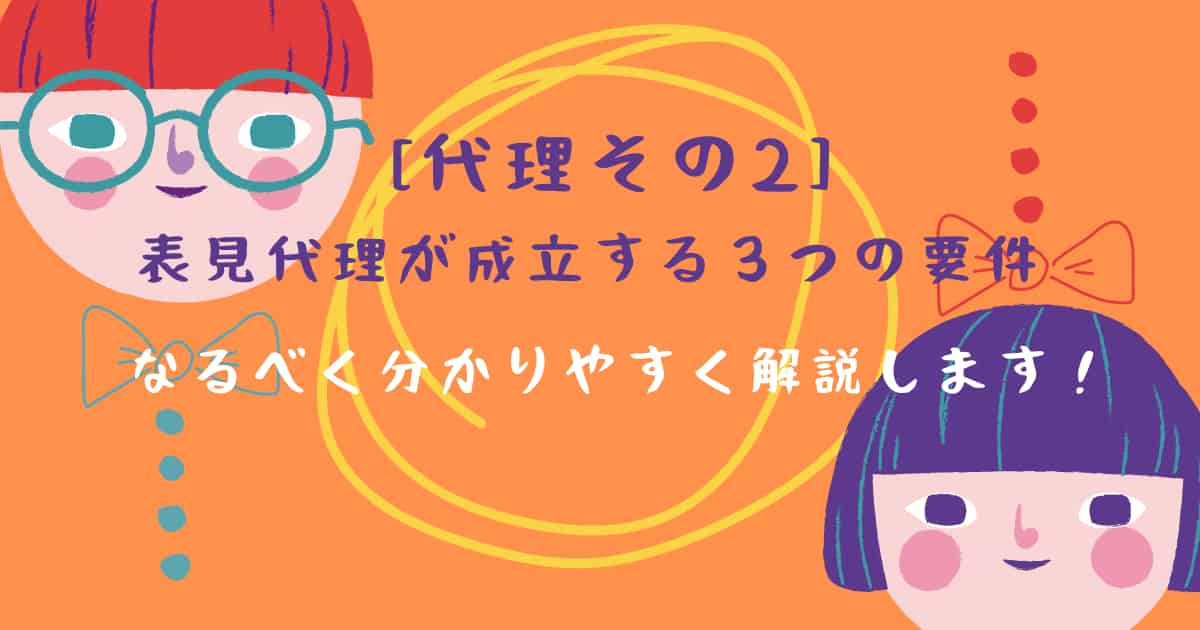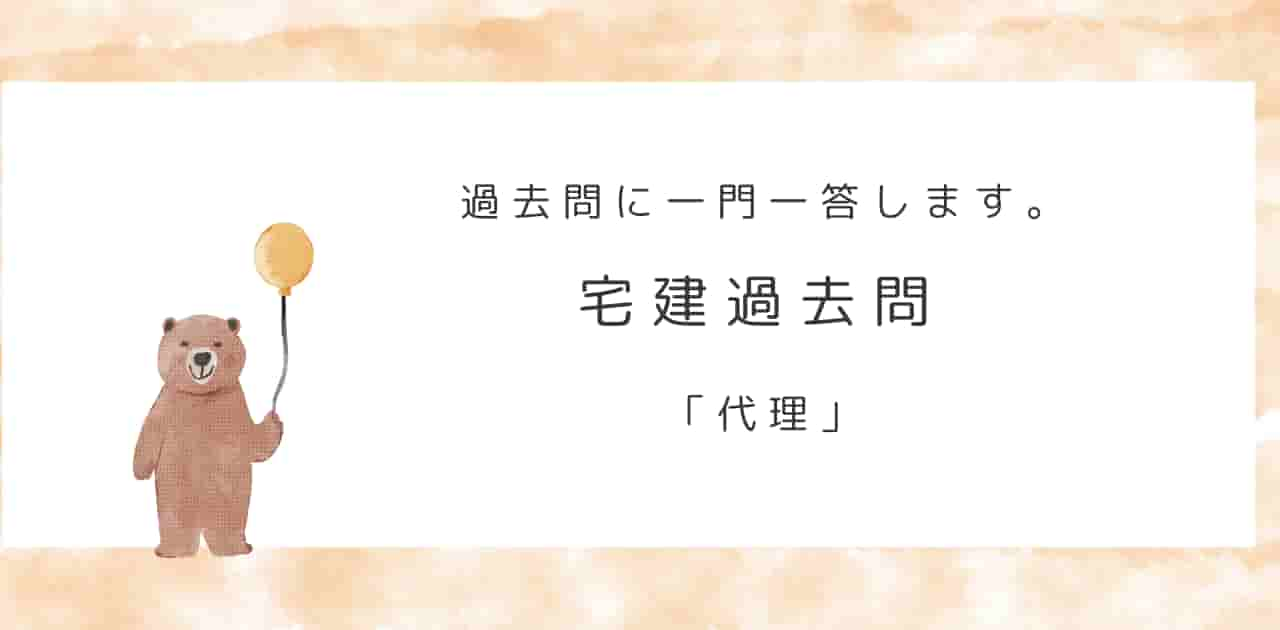「代理」の基本 分かりやすく解説します![宅建試験2023]

代理は宅建試験において、ほぼ毎年出題されている重要な箇所です!
まわりくどい文章に惑わされぬよう、問題を解く前に誰がどの立ち位置にいるのか、をイメージするようにしましょう!

漢字も読めないお馬鹿さんだったけど、独学2回目でなんとか宅建合格し、不動産屋さん歴11年目の寝子です。完全初心者~ほぼ初心者でも理解できるように分かりやすく解説していきます!
なるべくお金を掛けずにできる勉強方法とかも書いていく予定でーす
目次
|代理とは
●代理のしくみ
代理とは、本人に代わって法律行為等の意思表示をすることを言いますが、
民法では代理人がした意思表示の効力は直接本人に帰属(きぞく)するとされています。
例で説明すると、
AがBに自分の家を売る代理権を与え、Bに買主Cとの契約を結んでもらうとします。
そうするとAは直接Cとやり取りをしていませんが、AとCの間で契約が成立します。

本番では、この立場のAのことを本人、Cのことを相手方という呼び方をします!


つまり、Aは売主、Cが買主ということになります。
そして、Bの台詞のように代理人であることを言わないといけないよ。
そのことを顕名(けんめい)と言うよ!
もし、Bが本人Aの代理人であることを言わずに(顕名(けんめい)を欠く)代理行為をおこなった場合は、代理人自身が契約したことになってしまいます。
しかし、相手方Cが悪意(Aの代理で来たことを知っていた)や善意有過失(知り得た)の場合は、本人に効力が帰属します。
代理人が錯誤や詐欺・強迫にあってしまった場合、それを理由とする契約の取消権も代理人ではなく本人に帰属します。
つまり、契約を取り消せるのは本人だということです。
●制限行為能力者も代理人になれる
契約の効力は代理人ではなく本人に及ぶので、制限行為能力者も代理人になることができます。
たとえ、制限行為能力者が契約で損をしたとしても、不利な効果も本人に帰属するから、と考えると分かりやすいかな、と思います。
そしてその場合、本人は代理人が制限行為能力者であることを理由に取り消すことはできせん。

自分で代理人に選んだんだからそりゃそうだよね。
●復代理(ふくだいり) とは

たとえば、Aに代理権を与えられたBが交通事故にあって入院することになり、動けなくなったBはDに代理をお願いすることにしました。これを復代理と言います。
そしてこの時のDの立場を復代理人と言います。
代理人の時と同じく、復代理人がした契約の効力も本人Aに帰属します。つまりDはBの代理人ではなく、本人Aの代理人です!
🔑復代理の大事なポイント3つ
1⃣復代理人を選任しても代理人は代理権を失わない。
2⃣復代理人は代理人の代理権の範囲を上回ることができない。
3⃣代理人の代理権が消滅すると、復代理人の代理権も消滅する。
民法第104条
[任意代理人による復代理人の選任]
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

任意代理については↓で説明しまーす
●代理は2種類ある(任意代理・法定代理)
❶任意代理(にんいだいり):本人から頼まれて代理権を与えられた場合の代理
★この回で説明してきた例のような場合です。
❷法定代理(ほうていだいり):法律の規定によって代理権を与えられた場合の代理
★親権者や未成年後見人等がこれに当たります。

復代理人を選任するとき、違いがあるので覚えておきましょ~ 👇
どういう時に復代理人を選任できるか。
・任意代理人→本人の許諾を得た場合ORやむをえない理由がある場合。
・法定代理人→いつでも自由に選任できる。
例題:任意代理・法定代理の違い

・問題
(H24試験 問2):法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる→正しい
(H29試験 問1):委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。→正しい
民法第105条
[法定代理人による復代理人の選任]
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは 、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
民法第104条
[任意代理人による復代理人の選任]
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

ごっちゃにならないよーにね!
●代理人が禁止されていること2つ
代理人がやってはいけないことが2つあります。
禁止されているのも関わらず代理人がこの行為を行ったときは無権代理になり、本人に効果は帰属しません。
1⃣自己契約:例えばAが自分の家を売る代理権をBに与えたとして、代理人Bが買主となってその家を買うことを自己契約と言います。B自身が買主になると自分の有利な契約にしてしまう可能性があるからです。
※例外:Aの許諾OR追認があれば有効な代理行為となる。
2⃣双方代理:売主の代理人にも買主の代理人にもなってしまうことを双方代理と言います。
考えが相反する両者の代理人になり、両者の期待を満足させることは不可能なので禁止です。
※例外:両方の許諾があれば有効な代理行為となる。
|まとめ
今回は代理の基本を説明しましたっ。
この基本を押さえつつ無権代理に続きまーす